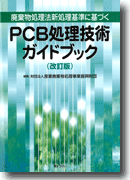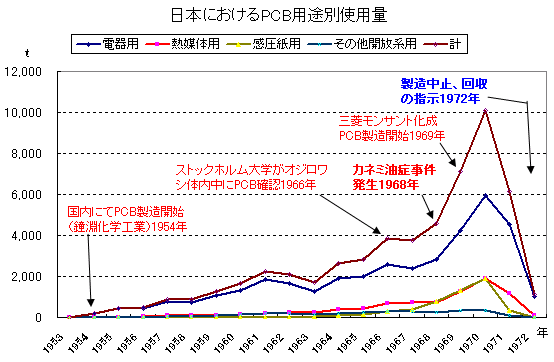|
PCB問題の概要
PCB処理技術ガイドブック(2005年8月改訂版)より 2005.12.24
第1部 PCB処理に関する概要(目次の紹介のみ)
第1章 PCB問題の概要 |
| 1.1 PCB問題の経緯 |
廃棄物処理法新処理基準に基づく
PCB処理技術ガイドブック(改訂版)
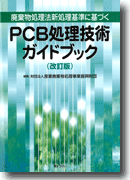
2005年8月1日発行
編集:財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
発行:株式会社ぎょうせい
定価(本体4,762円+税)
|
| 1,1,1 PCBの性状・生産・用途 |
| 1,1,2 PCBの保有 |
| 1,1,3 PCBの毒性及び環境中濃度 |
| 1.2 PCBの管理 |
| 1.3 PCBの処理 |
| 1.4 PCB廃棄物 |
| 1.5 最近の動向と処理基準の見直し |
| 1.6 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画 |
| 1.7 日本環境安全事業(株)の事業 |
★PCB問題の経緯
かって有用な物質として生産・使用されていたポリ塩化ビフェニル(PCB)は、カネミ油症事件をきっかけに生体・環境への影響があることが明らかになり、1972(昭和47)年までに生産が中止され、1974(昭和49)年度までに製造・輸入、開放系用途での使用、新規使用が禁じられた。閉鎖系用途については、その後熱媒体用のPCBは回収されたが、PCBが使用された電気器具は現在も継続して使用されているか、保管されている。
現在PCBは、労働安全衛生法の特定化学物質第1類物質、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第1種特定化学物質に指定され、生産、輸入、新規使用は禁止されている。
PCBに関する主な経緯を表1,1−1に、PCB及びPCB使用製品の生産中止の時期を表1,1−2に示す。
また、最近になって、PCBを使用していないとする重電機器の中に、微量のPCBが混入したものがあることが判明し、その処理の基本的方向等が検討されている。
表1,1−1 PCBに関する主な経緯
|
年
|
出 来 事
|
|
1881 (明治14)
|
ドイツのシュミット、シュルツ氏がPCB合成に成功 |
| 1929 (昭和4) |
米国スワン社(後にモンサント社に合併)工業生産開始 |
| 1954 (昭和29) |
国内にて製造開始(鐘淵化学工業(株)、三菱モンサント化成(株)(現、三菱化学(株))は1969(昭和44)年製造開始) |
| 1966 (昭和41) |
ストックホルム大学がオジロワシ体内中にPCB確認 |
| 1968 (昭和43) |
カネミ油症事件発生 |
| 1972 (昭和47) |
行政指導により製造中止、回収の指示(保管の義務) |
|
1973 (昭和48)
|
(財)電機ピーシービー処理協会((財)電機絶縁物処理協会と改称)が設立 |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、化審法という)制定。翌年以降PCB製造・輸入・使用の原則禁止 |
|
1976(昭和51)
|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)改正(PCB関係廃棄物の処理基準制定) |
| 電気事業法の省令改正、PCB使用機械器具の電路への施設禁止 |
1984 (昭和59)
|
通商産業省「PCB使用電気機器の取扱について」を通達
(保有状況に変化があった場合の報告先を明確化) |
| 1985 (昭和60) |
環境庁が鐘淵化学工業(株)高砂事業所の熱分解処理装置を用いて液状廃PCBを試験焼却 |
1987〜1989
( 昭和62〜平成元) |
鐘淵化学工業(株)高砂工業所において、液状廃PCB(約5,500トン)の高温熱分解処理を実施
|
1992 (平成4)
|
廃棄物処理法改正施行(廃PCB等及びPCB汚染物を特別管理産業廃棄物に、PCBを含む家電製品を特別管理一般廃棄物に指定) |
| 1993 (平成5) |
厚生省がPCB使用機器保管状況調査結果を公表 |
1997 (平成9)
|
廃棄物処理法施工令改正(PCB処理物を特別管理産業廃棄物に指定、処分方法としてPCBを分解する方法を新たに指定) |
| 1998 (平成10) |
廃棄物処理法の省令等改正(PCB廃棄物の処理基準設定) |
| 1999 (平成11) |
ダイオキシン対策特別措置法制定(PCB廃棄物処理施設は特定施設に該当) |
2000 (平成12)
|
厚生省がPCB使用機器保管状況調査を公表 |
| 廃棄物処理法の省令等改正(PCB汚染物の処理法として分解する方法を新たに指定) |
2001 (平成13)
|
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)採択(2004(平成16)年発効) |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物の処理計画と処理に関する規制強化)制定 |
| 環境事業団法改正(PCB廃棄物処理事業の実施とPCB廃棄物処理基金の設置) |
| 電気事業法の電気関係報告規制の一部改正(PCB使用電気機器の使用及び変更の届出規定) |
| (財)電機絶縁物処理協会解散 |
| 廃棄物処理法の省令等改正(PCB汚染物の処理法として分解する方法を新たに制定) |
| 環境事業団北九州事業第1期認可 |
2002 (平成14)
|
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の制定 |
| 環境事業団豊田事業、東京事業認可 |
| 微量PCB汚染機器の判明 |
2003 (平成15)
|
環境事業団大阪事業、北海道事業認可 |
| 低濃度PCB汚染物対策検討委員会の設置 |
2004 (平成16)
|
廃棄物処理法の省令等改正(PCB廃棄物として汚泥、コンクリートガラ等の追加、PCB廃棄物の収集運搬に関する規定、PCB廃棄物処理施設の記録/閲覧の規定等) |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の改定 |
|
環境事業団が日本環境安全事業株式会社(PCB廃棄物処理事業部門等)及び独立行政法人環境再生保全機構(PCB廃棄物処理基金等)に引き継がれる。
|
| 廃棄物処理法の関連告示改正(紙くず、木くず等の検定方法規定) |
表1,1−2 PCB及びPCB使用製品の生産中止の時期
|
生産者又は用途
|
生産・使用量(t)
|
中止時期
|
|
PCB
|
三菱モンサント化成(株) |
2,461
|
1972(昭和47)年3月 |
| 鐘淵化学工業(株) |
56,326
|
1972(昭和47)年6月 |
|
PCB使用製品
|
PCB入り感圧紙 |
5,350
|
1971(昭和46)年2月 |
| 塗料等の開放系用途 |
2,910
|
1971(昭和46)年末 |
| コンデンサ等の電気機器 |
37,156
|
1972(昭和47)年8月末 |
| 加熱機等の熱媒用途 |
8,585
|
1972(昭和47)年6月末 |
★PCBの性状・生産・用途
PCB(Polychlorinated biphenyl)ポリ塩化ビフェニルはビフェニル骨格に塩素が1〜10個置換したものであり、置換塩素の数や位置によって理論的に209種類の異性体が存在する。市販のPCB製品では約100種以上の異性体が確認されている。異性体間の物理・化学的性質や生体内安定性及び環境動態が多様であるため、PCBの化学分析や環境汚染の様式を複雑にしている。PCBの構造を図1,1−1(省略)に、PCBの同族体と異性体を表1,1−3(省略)に示す。
PCBの有する種々の特性としては、化学的に安定、熱により分解しにくい、酸化されにくい、酸・アルカリに安定、金属をほとんど腐食しない、水にきわめて溶けにくい、絶縁性がよい。高沸点、不燃性等があげられる。
PCBはこのように有用な特徴を有する物質として、1929(昭和4)年に米国で最初に工業化された。国内製品PCB(カネクロール、KC)の物理化学性状を表1,1−4(省略)に、米国の主要製品であるアロクロール(Aroclor)の物性を表1,1−5(省略)に示す。
我が国でも1950(昭和25)年頃から使用されるようになり、1954(昭和29)年から国内でも製造されはじめ、1972(昭和47)年までに約59,000トン(t)が生産された。日本における生産量を表1,1−6に示す。
PCBの用途としては熱媒体、トランス・コンデンサ用の絶縁油、ノーカーボン紙の他、潤滑油、各種可塑剤、塗料、シーラント剤等に使われていた。表1,1−7にPCBの用途と使われていた製品銘柄を示す。
表1,1−6 日本におけるPCBの生産量、輸入量及び用途別使用量(単位:t)
|
年
|
生産
|
輸入
|
国内使用量
|
輸出
|
|
電器用
|
触媒体用
|
感圧紙用
|
その他開放系用
|
計
|
|
1953
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
|
1954
|
200
|
−
|
200
|
−
|
−
|
−
|
200
|
−
|
|
1955
|
450
|
−
|
430
|
20
|
−
|
−
|
450
|
−
|
|
1956
|
500
|
−
|
430
|
50
|
−
|
20
|
500
|
−
|
|
1957
|
870
|
−
|
760
|
80
|
−
|
30
|
870
|
−
|
|
1958
|
880
|
−
|
740
|
100
|
−
|
40
|
880
|
−
|
|
1959
|
1,260
|
−
|
1,060
|
120
|
−
|
80
|
1,260
|
−
|
|
1960
|
1,640
|
−
|
1,320
|
170
|
−
|
150
|
1,640
|
−
|
|
1961
|
2,220
|
−
|
1,860
|
180
|
−
|
180
|
2,220
|
−
|
|
1962
|
2,190
|
3
|
1,640
|
240
|
10
|
200
|
2,090
|
100
|
|
1963
|
1,810
|
37
|
1,270
|
240
|
30
|
170
|
1,710
|
100
|
|
1964
|
2,670
|
8
|
1,920
|
400
|
100
|
210
|
2,630
|
40
|
|
1965
|
3,000
|
−
|
1,980
|
450
|
170
|
240
|
2,840
|
160
|
|
1966
|
4,410
|
117
|
2,600
|
660
|
300
|
270
|
3,830
|
580
|
|
1967
|
4,480
|
164
|
2,370
|
730
|
390
|
270
|
3,760
|
720
|
|
1968
|
5,130
|
223
|
2,830
|
720
|
780
|
260
|
4,590
|
540
|
|
1969
|
7,730
|
145
|
4,220
|
1,290
|
1,300
|
330
|
7,140
|
590
|
|
1970
|
11,110
|
181
|
5,950
|
1,890
|
1,920
|
360
|
10,120
|
1,000
|
|
1971
|
6,780
|
170
|
4,560
|
1,160
|
350
|
100
|
6,170
|
730
|
|
1972
|
1,457
|
−
|
1,016
|
85
|
−
|
−
|
1,101
|
758
|
|
計
|
58,787
|
1,048
|
37,156
|
8,585
|
5,350
|
2,910
|
54,001
|
5,318
|
出典:環境保健レポートNo14,(財)日本公衆衛生協会(1972)
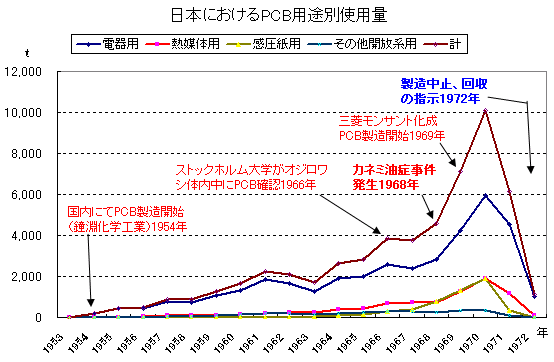
「 日本におけるPCBの生産量、輸入量及び用途別使用量」より作成
PCB及びPCB使用製品の生産中止の時期
|
生産者又は用途
|
生産・使用量(t)
|
中止時期
|
|
PCB
|
三菱モンサント化成(株) |
2,461
|
1972(昭和47)年3月 |
| 鐘淵化学工業(株) |
56,326
|
1972(昭和47)年6月 |
|
PCB使用製品
|
PCB入り感圧紙 |
5,350
|
1971(昭和46)年2月 |
| 塗料等の開放系用途 |
2,910
|
1971(昭和46)年末 |
| コンデンサ等の電気機器 |
37,156
|
1972(昭和47)年8月末 |
| 加熱機等の熱媒用途 |
8,585
|
1972(昭和47)年6月末 |
表1,1−7 PCBの用途と使用銘柄の例
|
用 途 大 別
|
製品例・使用場所
|
銘柄*
|
|
絶縁油
|
トランス用
|
ビル・病院・車両(地下鉄・新幹線ほか)・船舶などのトランス |
KC-1000 AroclorT100 |
|
コンデンサ用
|
蛍光灯・水銀灯の安定器用、洗濯機・ドライヤー・電子レンジなどの家電用、モーター用などの固定ペーパーコンデンサ、蓄電用のコンデンサ |
KC-300 Aroclor1242
400 1248
500 1254
|
|
熱媒体(加熱と冷却)**
|
各種化学工業、食品工業、合成樹脂工業などの諸工程における加熱と冷却、船舶の燃料油余熱、集中暖房、パネルヒーター |
KC-300 サントサーム 400 |
|
潤 滑 油
|
高温用潤滑油、作動油、真空ポンプ、切削油、極圧添加剤 |
KC-300他 |
|
可塑剤
|
絶縁油
|
電線の被膜、絶縁テープ |
− |
|
難燃用
|
ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、ゴムなどに混合 |
− |
|
その他
|
接着剤、ニス、ワックス、アスファルトに混合 |
KC-500 KC-C
600 |
|
塗料、印刷インキ
|
難燃性塗料、耐蝕性塗料、耐薬品性塗料、耐水塗料、印刷インキ |
− |
|
複 写 紙
|
ノーカーボン紙(溶媒)**、電子式複写機 |
KC-300(前者の複写紙) |
|
そ の 他
|
紙などのコーティング、自動車のシーラント、陶器ガラス器の彩色、カラーテレビ部品、農薬の効力延長材 |
− |
* KCはカネクロール、Aroclorはアロクロール、主として両社のカタログによる。
** PCBそのものが使われる。
出典:[厚生省環境衛生局]PCB関係資料(1972.4);官公庁公害専門資料vol.7,No3,p.35 |
|